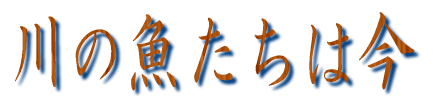 |
5.生命の川(ニ) |
| 1993年(平成5年)7月2日 |
| 水質が改善されてきたとはいえ、川の魚に関する問題の多くはまだ解決されていません。その証拠に、かつてはどの川でもごく普通に見られたメダカ、タナゴなどの魚は、現在まだ限られたわずかな水域に生息しているにすぎません。大多数の川では、生息する魚の種類数は昔より減っています。 つまり、汚濁をはじめとする環境の悪化に耐えられない種類の魚が姿を消し、これに耐えられる魚種だけが何とか生き残っているのです。例えば、かつての多摩川には、カジカという小魚が上流から下流域まで広く分布していました。ところが現在、この魚は奥多摩の渓流にまで行かねば見ることができません。 それでは、昔のような様々な種類の魚が豊富にすむ川の環境を取り戻してやることは、私たち人間にとってどんな意味を持っているのでしょうか。 もう十年近く前のこと、日本の自然保護運動のシンボル的存在で、多摩川の自然を守る会を主宰されていた故横山理子(さとこ)さんのお宅ヘお邪魔した時のことを、私は思い出します。 その日は、筑波大学の先生をなさっている御主人の十四男さんも同席され、理子さんと私の二人で多摩川についての話がはずみました。そのうち、御主人が理子さんの顔を見て、 「こういった自然保護運動というのは、生命を生み出す女性が、まず本能的な危険を感じて始めるものなのでしょうか。男性には欠けている何かがあるのかもしれませんね」と笑いながらおっしゃったのです。 それを聞いて私は「ああ、そういえば、 一九五〇年代にアメリカで環境問題に先鞭をつけたレイチェル・カーソンも女性だったな」と、何となく納得したものでした。カーソン女史の書いた「沈黙の春」は、今や世界中でこの分野のバイブル的存在となっています。 今はそういうことも少なくなりましたが、初期の自然保護運動は多分に自然の「愛護」活動的なものと見なされがちでした。ですから、「水をきれいにして魚のすめる川を取り戻そう」と訴えると、「魚と人間(の産業活動)のどちらが大切か」という答えがよく返ってきました。つまり、自然環境と経済をはかりにかけ、人間はお金の方を優先してきたのです。 しかしその後、飲料水の安全性についての知識が一般に普及してくるにつれて、川の汚濁はまさに人の生命に直結する問題であるという考え方が少しずつ浸透してきました。 川の水が汚れた結果、これを人の飲み水にするためには塩素剤による殺菌などの処理を施さなければなりません。しかし、こうした処理を行うと、近年話題になっているトリハロメタンをはじめ様々な有害物質が水の中に生じてくるというのです。これらの物質には発ガン性に加えて、遺伝子に突然変異を起こして子孫の代にまで影響を及ぼすという変異原性のあることが指摘されています。 さて、危険な水についての詳しい話は東京大学の中西準子氏の近著『いのちの水』など他書に譲ることとして、川の魚と人間の生命の関係を一言で表せば、 「魚のすめない川の水、人も飲めるわけがない」ということにでもなるのでしょうか。人々の飲み水に対する漠然とした不安を何よりも如実に物語っているのが、このところの空前の浄水器ブームであり、ミネラルウオーター消費量の急激な増加ぶりではないかと考えます。 |
